【大阪・関西万博】来場者1日20万人以上を記録!世界の文化を学べる漫画3選
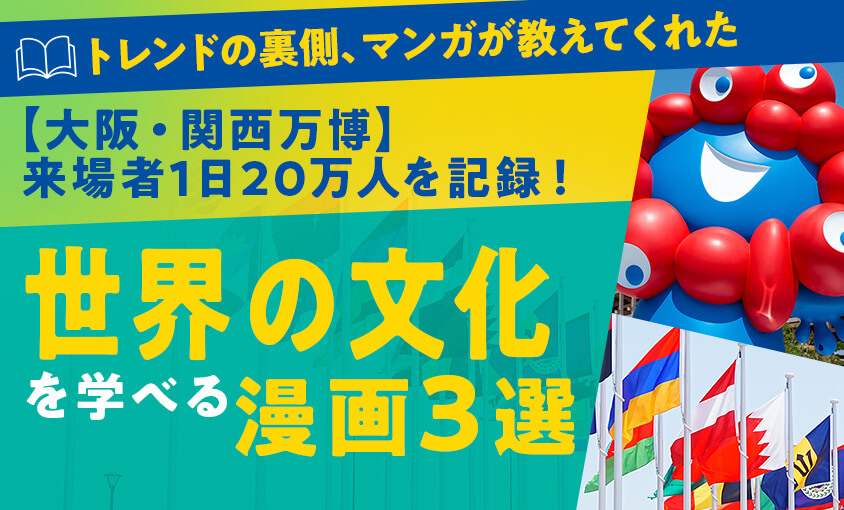
万博が生み出す世界文化との出会い
10月13日、半年間開幕していた大阪・関西万博が閉幕しました。来場者数が累計2,500万人以上、1日最高20万人以上を記録し、世界中から注目を集めました。国内開催では過去最多となる158カ国・地域、7国際機関が参加しました。特に注目すべきは外国人の消費単価で、8万7269円と関西以外在住の日本人(2万5164円)の3倍以上という数字が示すように、多様な文化背景を持つ人々が万博を通じて日本文化を体験しています。
さらに各国のナショナルデーでは本格的な文化紹介も展開されています。8月9日のペルー・デーではボルアルテ大統領が登場し、約150年の日本との交流史を紹介。スイスパビリオンでは女性の政治参加をテーマにした国際対話イベントが開かれ、各国の文化的価値観の違いが浮き彫りになりました。
このような多彩な世界文化との出会いを更に深く理解し、グローバル社会で生きる力を身につけるために、世界の文化を学べる漫画3作品をご紹介します。
国際交流について学べる漫画 3選
■『ヘタリア Axis Powers』(日丸屋秀和/2006年~)
世界各国を個性豊かなキャラクターで擬人化した本作は、大阪・関西万博で体験できる多様な国際交流を理解する上で最適な入門書です。イタリア、ドイツ、日本を中心に、各国の歴史的背景や文化的特徴、国民性の違いが分かりやすく描かれています。
万博会場で「外国人消費単価8万7269円」という数字の背景には、各国の経済状況や消費文化の違いがあります。本作では、そうした経済格差や価値観の相違が、キャラクター同士の関係性を通じて自然に理解できる構成になっています。また、歴史的な対立関係にあった国同士が現在では協力関係を築いているケースも多く描かれており、万博のような国際協調の場がなぜ重要なのかが見えてきます。特に第二次世界大戦を経た日本とヨーロッパ各国の関係変化は、現在の万博での友好的な交流の歴史的背景を理解するのに役立つでしょう。
■『テルマエ・ロマエ』(ヤマザキマリ/2008年~2013年)
古代ローマの浴場設計技師ルシウスが現代日本の銭湯文化と出会う本作は、異文化接触による驚きと学びを描いた傑作です。万博会場で「西アフリカのシチューやワニ肉パン」といった未知の食文化に出会う体験そのものが、ルシウスの体験と重なります。
作中で重要なのは、ルシウスが日本の入浴文化に最初は困惑しながらも、その背景にある技術や思想を理解していく過程です。万博のカナダパビリオンで「隣の女性が親切にアドバイス」をくれた体験や、シャトルバス内での情報交換も、こうした文化を超えた人間同士の共感や助け合いの現れです。本作は、言語が通じなくても、身振り手振りや表情で意思疎通が可能であることを実証しており、「お互いに楽しもう」という気持ちが国境を越える力を持つことを教えてくれます。
■『Dr.STONE』(稲垣理一郎・Boichi/2017年~2021年)
科学知識を武器に石器時代と化した世界を復興させる千空の物語は、万博が掲げる「未来社会のデザイン」というテーマと直結しています。作中では様々な民族や文化的背景を持つキャラクターが、科学という共通言語を通じて協力し合います。
万博のスイスパビリオンで開催された「女性の政治参加」をテーマにした国際対話イベントのように、共通の課題解決に向けて国境を越えて協力する姿勢が重要です。本作では、司帝国や百夜村など異なる価値観を持つ集団が、最終的には人類全体の復興という大きな目標のもとで連携していきます。これは万博で263万人の外国人来場者と973万人の日本人来場者が、文化の違いを越えて同じ体験を共有している状況と通じるものがあります。科学技術の発展が人類共通の利益につながることを描いた本作は、国際協力の本質を理解する上で貴重な視点を提供してくれます。
3つの漫画で学べるポイント
今回紹介した3作品から学べるのは、大阪・関西万博で実際に起きている国際交流の本質的な価値です。
『ヘタリア Axis Powers』では、外国人来場者の消費単価が日本人の3倍以上という数字の背景にある、各国の経済状況や文化的価値観の違いを理解できます。キャラクター化された各国の特徴を通じて、万博会場で出会う多様な国々の歴史的背景や現在の国際関係が見えてきます。ペルー・デーでボルアルテ大統領が語った「150年の日本との交流史」のような長期的な外交関係も、本作で描かれる国同士の関係変化と重なる部分が多いでしょう。
『テルマエ・ロマエ』からは、言語の壁を越えた人間同士の共感力を学べます。万博会場で「隣の女性が親切にアドバイス」をくれたり、シャトルバス内で初対面同士が情報交換したりする光景は、まさにルシウスが体験した異文化理解のプロセスそのものです。西アフリカのシチューやワニ肉パンといった未知の食文化に出会う驚きも、作中でルシウスが日本の銭湯文化に触れた時の感動と同質のものといえます。
『Dr.STONE』では、共通の目標や課題を通じた国際協力の重要性を理解できます。スイスパビリオンで開催された女性の政治参加をテーマにした国際対話のように、人類共通の課題解決に向けて国境を越えて協力する姿勢の大切さが学べます。万博という場が単なる展示会ではなく、未来社会のデザインを各国が共同で考える場である意義も、作中の科学技術を通じた人類復興の物語から深く理解できるでしょう。げが続く時代に家計をどう守るかのヒントが得られるでしょう。
まとめ – 万博体験を日常に活かす文化理解
大阪・関西万博で1日最高20万人が体験している世界文化との出会いは、単なる一時的なイベントではありません。外国人263万人、日本人1500万人以上が同じ空間で多様な文化に触れ、自然発生的な交流が生まれている現場は、まさに理想的な国際社会の実現例といえるでしょう。
今回紹介した3つの漫画は、この万博体験をより深く理解し、日常生活でも活かせる世界文化への理解力を養うための実践的な教材です。『ヘタリア』で学ぶ各国の文化的特徴、『テルマエ・ロマエ』で体験する異文化接触の驚きと発見、『Dr.STONE』で描かれる文化を超えた人類共通の価値——これらすべてが、万博会場で実際に起きている体験と直結しています。
万博での世界文化体験を単なる観光で終わらせず、これらの漫画から得た知識と組み合わせることで、真の国際理解を深めてみませんか?
