戦後80年! いま読んでおきたい戦争について学べる漫画3選
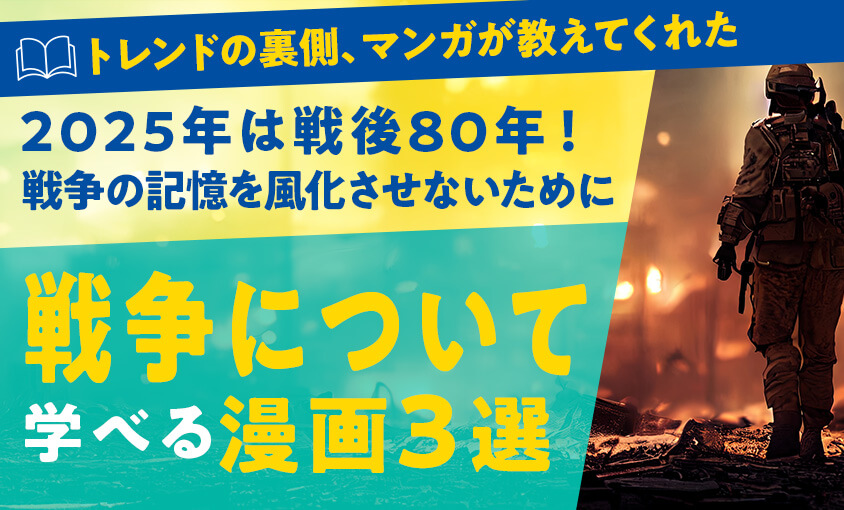
日本にとって忘れてはならない4つの日
上皇陛下(第125代天皇)が皇太子時代に「忘れてはならない日」として、戦争にまつわる4つの日をあげたことにともない、宮内庁のウェブサイトにも「忘れてはならない4つの日」というタイトルで掲載されています。
4つの日とは、下記のとおりです。
- 沖縄慰霊の日(6月23日)
- 広島原爆の日(8月6日)
- 長崎原爆の日(8月9日)
- 終戦の日(8月15日)
引用:宮内庁|戦没者慰霊
沖縄では1961年より毎年6月23日に沖縄全戦没者追悼式、広島では1947年より毎年8月6日に広島平和記念式典、長崎では1948年より毎年8月9日に長崎原爆犠牲者慰霊平和祈念式典、終戦の日には1952年より毎年8月15日に全国戦没者追悼式が開催されています。
厚生労働省の調査によると、被爆者健康手帳を持っている人は99,130人。1957年の交付開始以来はじめて10万人を下回りました。その一方で高齢化も深刻な問題で、平均年齢は86.13歳です(2025年3月末時点)。
戦争経験者・被爆者の高齢化が進んでいる現在、そうした出来事の記憶を次世代に引き継ぐことは、今後の私たちにとって大きな課題といえるでしょう。 そこで、今回は【戦争について学べる漫画】をテーマに、3つの作品を紹介します。
戦争について学べる漫画 3選
■『戦争は女の顔をしていない』(原作:スヴェトラーナ・アレクシエーヴィチ、作画:小梅けいと/2019年~)
1941~45年にかけて行われた独ソ戦とは、第二次世界大戦中に当時のナチス・ドイツとソビエト連邦の間で行われた戦争です。第二次世界大戦時のソ連軍では、80~100万人の女性が志願して従軍したと言われています。戦闘に参加したことを政府から称賛され、象徴となった女性兵士やパルチザンもいた一方、セクハラやパワハラ、ストーカー行為を受ける女性も多くいたのです。
原作となる小説は、500人以上の従軍女性からの証言を記録・編纂したものを、1985年にノンフィクション小説として発表。2019年よりウェブコミックサイトのカドコミにて、小梅けいと先生によるコミカライズがはじまりました。戦場では人格や個性を奪われながら振る舞うことを要求される中、なお人間としての尊厳を守ろうとする女性たちの姿が繊細な絵柄で描かれている作品です。
【楽天市場】戦争は女の顔をしていない – 小梅けいと の検索結果
■『この世界の片隅に』(こうの史代/2007~2009年)
主人公は、浦野すずという18歳の女の子。物語は、1943年12月の日常からはじまります。妹と一緒に祖母の家で仕事を手伝っていたある日、縁談の話が舞い込み、4歳年上の北條周作(呉の北條家)のもとへ嫁ぐことに。不器用で危なっかしく見えるすずは、小さな失敗を繰り返し小姑から小言を言われるものの、持ち前のユーモアや生活の知恵を発揮して、北條家や近所の人から受け入れられていきます。
そんな中、戦況は悪化して呉市も空襲の対象となり、やがて広島市内に原爆が投下され、当日爆心地にいた人、親族の様子を確認に訪れた人が次々に被爆していきます。本作は、広島の呉市を舞台に自然の美しさや命の輝き、戦時中に生きた人の創意工夫を描いた物語であるとともに、のんきで明るい主人公が、大切なものを戦争に奪われながら希望を取り戻して生きていく物語です。
■『国境のエミーリャ』(監修協力:津久田重吾、作画:池田邦彦/2019年~)
私たちが社会科もしくは日本史で教わったのは、ポツダム宣言を受諾して、9月2日に降伏文書へ調印したことで第二次世界大戦が終結したという史実です。しかし、宣言を黙殺して、戦争を継続しようという動きもありました。もしも、ポツダム宣言を受け入れずに本土で内戦が続いていたら、日本はどうなっていたのでしょうか。
舞台は、徹底抗戦の末に敗れた後、冷戦の激化に伴ってソ連統治地区の東側が日本人民共和国(東日本国)、米英統治地区の西側が日本国として独立した1962年の日本。東京は東東京と西東京で分割されています。昼は十月革命駅(旧上野駅)に併設するレストランで給仕係として働く、19歳の女性・杉浦エミーリャが主人公です。そんな彼女のもうひとつの顔は、東から西へと人々を逃がす「脱出請負人」。
本作では「米国・英国・ソ連による分割統治」という、もうひとつあり得た歴史の「if」を描いています。
3つの漫画で学べるポイント
今回紹介した3作のうち『戦争は女の顔をしていない』のテーマは、第二次世界大戦の中でもっとも多くの被害者が出たとされる独ソ戦において、実際に従軍した女性500人以上の証言の記録です。
ソ連軍に従軍した女性は、医療・看護・調理・洗濯・戦闘などに従事。本作では、従軍女性がソ連軍の中で携わっていた仕事の他、夫婦二人で出征していた女性の証言が描かれています。戦場の極限状態にあり、人格や個性、揺れる心を隠さなければならない中、人としての尊厳を守ろうと必死な姿は、私たちがどう生きるべきかを示しているようです。
『この世界の片隅に』は、横須賀や佐世保と並ぶ軍港都市だった広島県呉市を舞台にしています。本作のテーマは、少しずつ戦争の足音が大きくなっていく中、一般市民がどのように生活を営んでいたのか、戦争によってどのように変化していったのかです。
特に広島市内で出会った戦災孤児が、すずに懐いて呉の自宅に連れて帰るシーンは、戦後間もない広島で本当にありそうな描写で、平和であることの尊さを感じさせます。
『国境のエミーリャ』は、今回紹介した3作の中では唯一史実に基づいたものではなく、ポツダム宣言受諾を拒否した世界で起きていたかもしれない「歴史の可能性」がテーマです。もし、日本が本土決戦を選択していたら、本当に本作のような東西分割の世界線が見られたかもしれません。
北海道から東北、関東の一部がソ連、神奈川県より西は米英が統治。首都東京は、東と西の境が壁で完全に分断されており、旧東西ドイツのベルリン(当時の東ベルリン・西ベルリン)のようになっていたでしょう。 また、時代背景と作者のレトロな絵柄が絶妙で、旧ソ連式の政治・経済、生活・文化が取り入れられている日本と、冷戦下における共産国家の冷たい空気感という、現実には起きていないが起こっていたかもしれない仮想現実を突きつけてきます。
まとめ – 戦争の記憶が風化する前にできることとは
各作品で扱っているテーマ・描き方に違いはあるものの、どの作品にも共通しているメッセージが、平和であることの大切さです。主人公は、取り上げた作品順に従軍していた女性もいれば、戦時中の日本で暮らす女性、東日本(東西に分割された日本)で暮らす日本人と、主人公の立場は異なります。しかし、どの作品でも平和を願いつつ、日常生活のありがたさを味わいながら生きている描写がなされていました。
戦争の悲惨さ、平和の尊さを知るには、広島や長崎、沖縄で語り部の体験記を聞くのが一番なのは言うまでもないでしょう。しかし、彼らも高齢化でなかなかこのような活動に参加できなくなりつつあります。
今も世界では、ウクライナ侵攻やアフガニスタン紛争、ミャンマー内戦など、さまざまな紛争・戦争が起きているのが現実です。その中で、日本は戦後80年、大きな紛争・戦争に巻き込まれることなく来ています。戦争を知る世代の高齢化で記憶が風化してしまう前に、これらの漫画から戦争の悲惨さや平和の尊さを知る機会を得てみませんか?
(執筆: なつめれいな)
